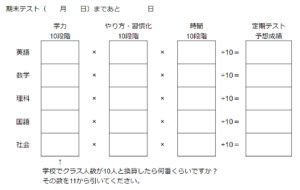地震雷火事親父
「地震雷火事親父」
(じしん・かみなり・かじ・おやじ)
今回の台風でこの言葉をふと思い出しました。
最近はあまり聞きませんが、ものすごく怖いものを並べて、リズミカルに表した言葉。
しかし本当はこの「親父」の部分はもともと「大山風」(おおやまじ)、または「大風」(おおやじ) だったとか。
つまりは台風のこと。
「大山風」という言葉自体をあまり使わなくなったせいもあり、転じて、ゴロのよい「親父」が主流になったと。
さて、、、
現在の世の親父さんは台風くらい恐いのでしょうか?
私は山の中腹に住んでいますので、今回の台風では大好きな樹々が沢山折れたり、根こそぎ倒れていて、少なからずショックを受けております。
美しかった竹林。青竹までが沢山折れています。写真で見るより実際はもっと無残です。

街路樹や大木が沢山折れて風で飛ばされています。

自然の猛威は人知の及ばぬ強大な力で、よく言えば人間の安穏とも思えた営みの脆さ、思い上がりを突如気づかせ、戒めてくれます。
地震も、雷も、火事も、台風も、とても恐ろしいがなぜか「嫌い」だとは言いません。誰でも恐ろしいものは嫌いに決まっています。そしてもちろん好きでもありませんが、本能的に起こりうる脅威を、畏れ、思い起こす度に自らを戒め、戒めがある種の自然神格化したようなものになっているのかも知れません。
今は何でも言葉にしないと意味がないとか、価値がないと言われます。
そんな風潮にふと違和感を持つことがあります。
違和感は大事です。
違和感があるから危険を回避できたり、真実に近づけます。
違和感を大切にして、ずっと先で自分なりの答えが見つかることも、普遍的に答えが出ないものだという答えに行きつくこともあると思います。
言葉にできないこと、
その大切さ。
「畏敬の念」という言葉があります。
=自然など言葉にはできない圧倒的な力や存在を前にして、慎しみ深く、謙虚で、厳粛な気持ちになること。
現代人はこれを忘れてしまっているのではないでしょうか?
子どもたちを見てください。
周囲に「畏敬の念」を感覚的に理解している子どもがどれほどいるでしょうか?
インスタントな欲望を満たすものが溢れ、到底そんな感覚に行き着かない。
子どもは大人を映す鏡です。
大人は思ったことをすぐに口に出すのではなく、
もっと言葉を大事に慎重に使って、
また言葉にできない大切な感覚を忘れずに、
そしてその姿勢を次の世代の子どもたちにも
しっかり伝えていかないといけませんね。
そういう意味では台風よりも身近にある「恐ろしい親父の存在」は、それこそ「非常に恐ろしく有り難かった」のかも知れませんね。
おわり